概要
Overview膀胱に炎症が起こることが原因となり、血尿、頻尿、排尿時の痛みなどの症状が見られる病気が膀胱炎です。排尿困難や血尿などの泌尿器症 状を引き起こす「猫下部尿路疾患(FLUTD)」(※)の要因の1つです。
猫の膀胱炎は、ブドウ球菌や大腸菌等の細菌感染が原因となって起こる「細菌性膀胱炎」と細菌感染などの明らかな原因が見られないにもか かわらず膀胱炎の症状が見られる「特発性膀胱炎」とに大きく分けられます。
人や犬では「細菌性膀胱炎」が多いのに対し、猫では原因の分からない「特発性膀胱炎」が多く見られます。「特発性膀胱炎」はストレスが 発症要因の一つだと言われており、比較的若い猫に多く、治っても再発しやすいという特徴があります。
※猫下部尿路疾患(FLUTD: Feline Lower Urinary Tract Disease)
猫の下部尿路(膀胱、尿道)に起こる病気全般を総称して猫下部尿路疾患(FLUTD)と呼びます。原因には膀胱炎の他、尿路結石、膀胱 腫瘍なども含まれます。
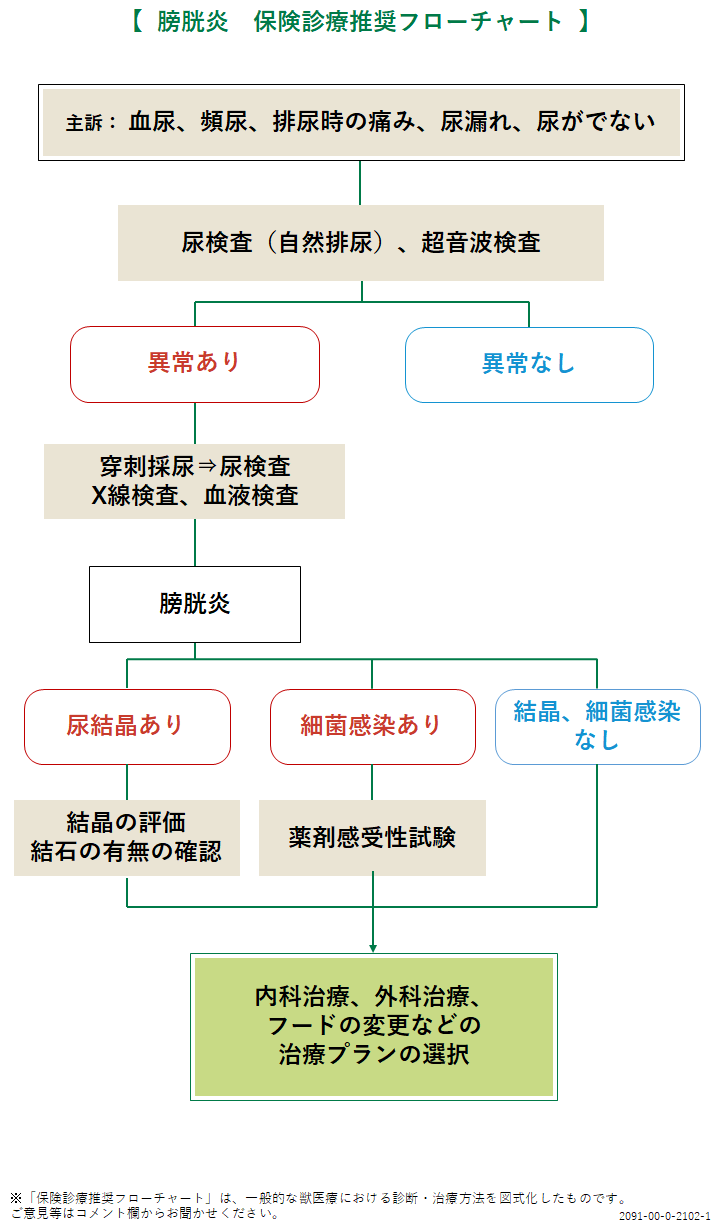
※コメント欄は、同じ病気で闘病中など、飼い主様同士のコミュニケーションにご活用ください!記事へのご意見・ご感想もお待ちしております。
※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。
お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト
原因
■細菌性膀胱炎の場合
膀胱内に侵入したブドウ球菌や大腸菌等の細菌が原因となって膀胱に炎症が起きます。また、膀胱内に生じた結晶や結石が膀胱粘膜を傷つけ、そこに細菌が感染することによって引き起こされることもあります。
■特発性膀胱炎の場合
「特発性」というのは、原因が特定できない、あるいは不明だという意味ですので、特発性膀胱炎は特に原因が見当たらないのに頻尿や血尿などの膀胱炎の症状が見られることをいいます。尿検査をしても、細菌感染や尿石、結晶、異常な細胞などの原因は見つかりません。
直接的な原因ははっきり分かっていませんが、発症要因として「尿が濃縮することで膀胱粘膜が刺激を受けやすくなって異常が起きる」、「神経伝達物質の刺激で炎症を起こした細胞が膀胱に影響を及ぼしている」などの可能性が考えられています。また、多頭飼育などのストレスの多い環境で飼育 されている猫やストレスを感じやすい性格の猫で発症しやすい傾向が見られるため、ストレスも発症の要因の一つではないかと考えられています。
症状
頻尿(トイレに頻繁に行くが少量しか尿が出ない)や血尿、不適切な場所での排尿、排尿時の痛み、食欲不振、元気消失などの症状が見られます。特発性膀胱炎では、ストレスを強く感じるような状況下での発症や悪化が見られることがあります。
また、尿道が太い女の子の猫ではあまり見られませんが、尿道が細い男の子の猫では、膀胱炎の影響で尿中に大量に出てきた炎症細胞や膀胱粘膜の細胞が固まりとなり、細くなっているペニスの先の尿道部分を塞いでしまい尿が出ない状態(尿閉)になってしまうことがあります。また、膀胱が激しい炎症を起こすと、膀胱の筋肉が緊張して尿が出せなくなり、尿閉状態になってしまうこともあります。尿を出せない状態が続くと、膀胱内の尿が腎臓に逆流し、腎不全や尿毒症を引き起こすことがあります。尿毒症になると、嘔吐や体温の低下といった症状が見られ、生命にかかわることがあります。
治療
■細菌性膀胱炎の場合
細菌感染を抑えるため抗生剤を投薬します。なかなか改善が見られないときには、尿中の細菌培養検査等を行い、投薬する抗生剤の種類を再検討することもあります。また、尿路結石が原因となっている場合には、膀胱炎の治療と並行して、結晶や結石の治療やケアをすることがあります。
■特発性膀胱炎の場合
特定の原因が見当たらないので、原因を除去するための治療はできません。薬物療法は、痛みが強い時に鎮痛剤を使用したり、炎症による筋肉の強い緊張により排尿が上手くいかない時には排尿を助ける薬物を使用するなど、対症療法的なものとなります。また、ストレスを軽減する目的で抗不安薬などのお薬やサプリメントを使用することがあります。これに加えて特発性膀胱炎の治療では、次のような「ストレスを減らし、頻繁な排尿を促すための生活環境と生活習慣の見直し」が重要です。
1.ストレスの除去
特発性膀胱炎の原因の一つとして、ストレスの関与が指摘されています。ストレスの要因となるのは、トイレ環境、多頭飼育、引っ越し、生活パターンの変化、食事の変更、家族の変化など様々です。何かにストレスを感じている様子があれば、原因となることを取り除くようにしましょう。
また、身を隠すことができる場所を確保するなど、できるだけ穏やかに生活できる環境を提供してあげることも必要です。
2.トイレ環境の見直し
膀胱炎の予防には「トイレを我慢せず、水分をたくさんとって十分に排尿すること」が重要です。トイレ環境に神経質な猫が多いので、排尿しやすいトイレ環境を用意してあげましょう。
トイレの数は、「お家にいる猫の数+1個、留守の多いお家ではそれ以上必要」だといわれています。大きさは猫の体長の1.5倍くらいで、屋根や扉がなく開放的なトイレを好む猫が多いようです。砂のタイプの好みもいろいろですので、数種類の砂を用意して、猫自身が好きな砂を選ぶようにすると良いでしょう。
トイレの場所についても、暑さ寒さなどの影響を受けず、どんなときでも落ち着いて使用できる場所であるかを確認してみましょう。汚れたトイレでの排泄を嫌がり我慢をしてしまう猫もいますので、排泄をしたらすぐに片付け、砂の交換やトイレ容器の洗浄などもこまめに行い、常に清潔を保つことも必要です。
3.水分摂取量を増やす
濃い尿は膀胱粘膜を刺激しますので、水分をたくさんとって尿を希釈し、頻繁に排尿することでオシッコが長い時間膀胱内に留まらないようにすることが理想です。猫の飲み水の好みは、汲み置きの水が好きな猫もいますし、蛇口から流れ出る水を好む猫もいて、様々です。また、お気に入りの置き場所も静かな所、ご家族の近く、窓の近くの外が見える場所など様々です。お気に入りの場所で好みのタイプの水が飲めるようにしてあげましょう。
普通の水をなかなか飲んでくれない場合には、脂身の少ない鶏肉やお魚などを煮出して脂を取り除いたスープや野菜を煮出して作ったスープ、缶詰やドライフードを少量加えて溶かした状態の水などを飲んでくれる場合もありますので、試してみるのも一つの方法です。飲み水に混ぜて嗜好性を上げるための液体状のサプリメントなどもあります。また、フードをドライからウェット(缶詰)に変えたり、ドライフードを水やお湯でふやかすことでも水分摂取量を増やすことができます。
予防
原因にかかわらず膀胱炎の予防としては、「できるだけストレスを与えないこと」、「トイレを我慢させないように排尿しやすい環境を作ること」、「水分をたくさん摂らせること」が重要です。また、膀胱炎は「早期発見・早期治療」が重要ですので、日頃から水の飲む量やトイレの回数、尿色や量などをきちんと確認しておき、変わった様子が見られるときには早めに受診するようにしましょう。
他の動物種のデータを見る
- 犬全体
- 大型犬
- 中型犬
- 小型犬
- アイリッシュ・セター
- 秋田犬
- アフガン・ハウンド
- アメリカン・コッカー・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気は?
- アラスカン・マラミュートってどんな犬?気を付けたい病気はある?
- イタリアン・グレーハウンド
- イングリッシュ・コッカー・スパニエルってどんな犬種?なりやすい病気は?
- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル
- イングリッシュ・セター
- イングリッシュ・ポインター
- ウィペットってどんな犬種?気を付けたい病気はある?
- ウェルシュ・コーギー・カーディガン
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- ウェルシュ・テリア
- ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア
- エアデール・テリア
- オーストラリアン・シェパードってどんな犬種なの?特徴や気を付けるべき病気は?
- オールド・イングリッシュ・シープドッグ
- 甲斐犬
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!
- グレート・デーン
- グレート・ピレニーズってどんな犬種?気を付けたい病気は?
- ケアーン・テリア
- コリー
- コーイケルホンディエ
- ゴールデン・レトリーバー
- サモエド
- サルーキってどんな犬種?気を付けたい病気はある?
- シェットランド・シープドッグ
- 柴犬
- シベリアンハスキー
- シーリハム・テリア
- シー・ズー
- ジャック・ラッセル・テリア
- ジャーマン・シェパード・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気は?
- スキッパーキ
- スコティッシュ・テリア
- スタッフォードシャー・ブル・テリア
- セント・バーナード
- ダックスフンド(カニーンヘン)
- ダックスフンド(スタンダード)
- ダックスフンド(ミニチュア)
- ダルメシアン
- チベタン・スパニエル
- チャイニーズ・クレステッド・ドッグ
- チャウ・チャウ
- チワワ
- 狆(ジャパニーズ・チン)
- トイ・マンチェスター・テリア
- ドーベルマン
- 日本スピッツ
- 日本テリア
- ニューファンドランドってどんな犬種?気を付けたい病気は?
- ノーフォーク・テリア
- ノーリッチ・テリア
- バセット・ハウンドってどんな犬種?太りやすいって本当?
- バセンジー
- バーニーズ・マウンテン・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!
- パグ
- パピヨン
- ビアデッド・コリー
- ビション・フリーゼ
- ビーグル
- 外で遊ぶのが大好き!フラットコーテッド・レトリーバーってどんな犬種?
- フレンチ・ブルドッグ
- ブリタニー・スパニエル
- ブリュッセル・グリフォン
- ブルドッグ
- ブル・テリア
- プチ・バセット・グリフォン・バンデーン
- プードル(スタンダード)
- プードル(トイ)
- プードル(ミディアム)
- プードル(ミニチュア)
- プーリー
- ベドリントン・テリア
- ベルジアン・シェパード・ドッグ(タービュレン)
- ペキニーズ
- 北海道犬
- ボクサー
- ボストン・テリア
- ロシアが誇る美しい狩猟犬、ボルゾイについて|気を付けたい病気を解説!
- ボロニーズ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- ポリッシュ・ローランド・シープドッグ
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ピンシャーってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!
- ヨークシャー・テリア
- ラサ・アプソ
- ラブラドール・レトリーバー
- レオンベルガーってどんな犬?気を付けたい病気はある?
- レークランド・テリア
- ロットワイラー
- ワイアー・フォックス・テリア
- ワイマラナーってどんな犬種?気を付けたい病気は?








特発性膀胱炎の場合、ストレスを軽減するための生活環境や生活習慣の見直しで良化することもありますが、症状が続く場合はお薬による治療が必要なこともあります。また、頻尿や血尿の場合、特発性膀胱炎だけではなく、細菌感染や尿結石が原因となっていることもあります。原因により治療も変わってくるため、検査や治療について、かかりつけの先生にもご相談されることをお勧めいたします。
細菌感染による膀胱炎の場合、有効な抗生物質の投与により感染が抑制され、炎症がおさまると頻尿も落ち着いてきます。ただ、治癒までの期間はネコちゃんの状況と個体差により数日から数週間など大きく変わります。水分摂取量に関しては、膀胱結石など他疾患の併発などにより増やすことが良い場合もありますが、ネコちゃんの状況により異なりますのでかかりつけの先生にご相談をお願いします。
抗生物質を処方され飲ませていますが 何日位で頻尿は落ち着いてきますか?
それと水分量は何時もより増やした方がいいのですか?
おしっこを頻繁にする、ふんばっても少ししかでないなど、いつもとおトイレの様子が違う場合、膀胱炎などの泌尿器系のトラブルが起こっている可能性もございます。
早期対応が大切となりますので、お早めに動物病院に行かれることをおすすめいたします。